OUR WORKS
事例
株式会社ジャックス「あなたの挑戦」が会社をつくる。これまでを紐解き未来に紡いだ70周年記念誌

コーポレートコミュニケーション部
部長 舛水 隆史
課長 小林 伸之
穴田 理絵
石川 由梨子
創業70周年を機に記念誌を制作した株式会社ジャックス(以下、ジャックス)。
「ジャックスらしい」をキーワードに、単なる歴史の記録ではなく、これからをつくる従業員一人ひとりの未来への挑戦を喚起させるというコンセプトで制作。コンセプトづくりから企画編集、制作と発行までに1年7カ月を費やしました。壮大なプロジェクトを無事に終えた今、編纂メンバーの率直な思いや学びを伺いました。
迷いながらも「ジャックスらしさ」を追求したコンセプトづくり
「コンセプトを固めるまでが本当に大変でした」と語るのは、社内報制作の経験がある石川さん。「これまでの觀念にとらわれず、一から何を掲載するべきか、どのような記念誌を目指すのか、白紙の状態から考え直しました。コンセプトづくりの際には、入社面接のような…(笑)、『なぜジャックスに自分が入社したのか?』『ジャックスの好きなところは?』などの、自分たちへの問いを通じて、会社に対する想いや今の課題を掘り下げるワークから始めたことを覚えています」。
編纂メンバー4人は何度も議論を重ね、「ジャックスらしい」記念誌を模索。固定観念にとらわれず、史実の裏にある従業員一人ひとりが大切にしてきた想いや誇り、そして「堅実」の裏にある「挑戦の歴史」を浮き彫りにする手法を選びました。
コンセプトが決まり、ページ構成が決定した後も、「ページ数が多く、チェックする人も多いという点で非常に大変でしたが、2500人以上いる会社の中で、この仕事ができたのは貴重な経験でした」と石川さんは振り返ります。
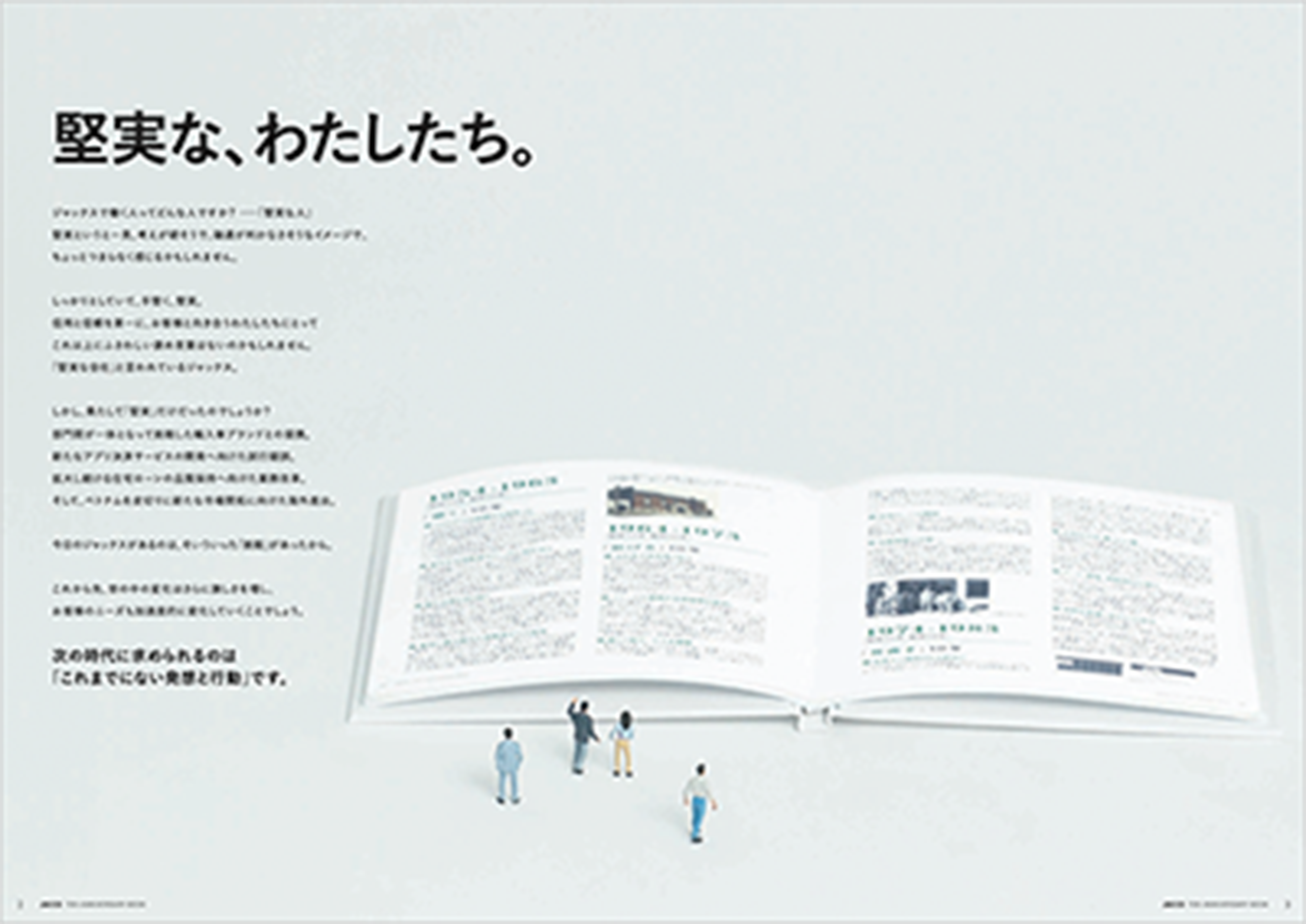
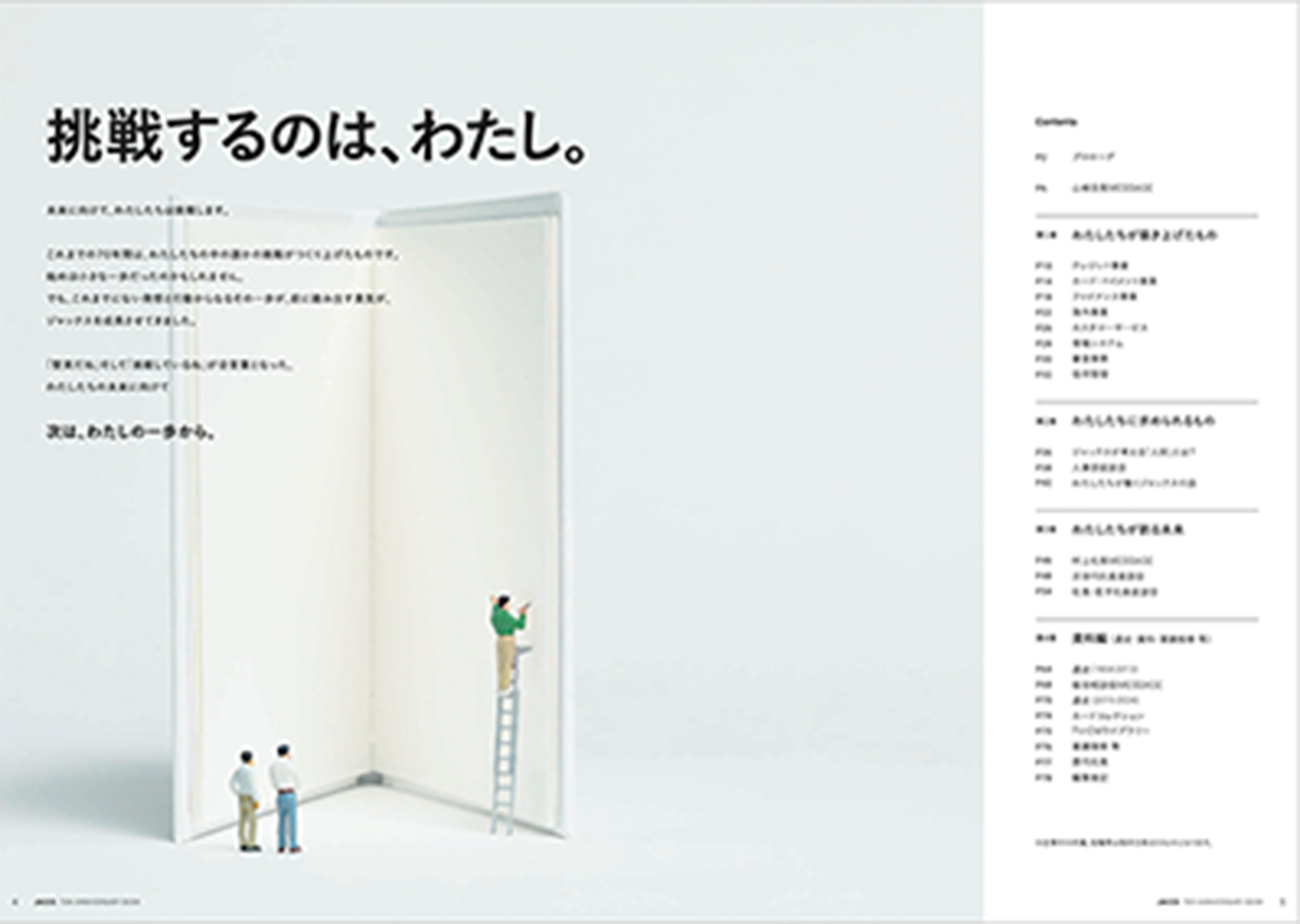
ただ歴史を紡ぐだけではない読み手を意識した編纂

プロジェクトを進める中で、メンバーの意識にも変化がありました。「正直、コンセプトづくりの段階では、どういうものが出来上がるのか全く想像がつかず、不安も大きかったです」と穴田さんは当時を振り返ります。
「プロジェクトの初期は、過去を振り返るための記念誌という思いが先行していましたが、原稿や紙面が仕上がっていく中で、次第につくりたいものが明確になってきました。出来上がったものを見ると、本当に良いものができたと感じています。特に発刊後の従業員アンケートで集まった未来に向けた前向きなメッセージを見ると、つくって良かったという想いが強くなりました」。
また、小林さんは「自分が入社した年にちょうど50周年記念誌が発行されたのですが、社歴が浅かったこともあり、当時はその価値を十分に理解することができませんでした。今回、自分自身が記念誌を編纂する立場になり、20年の期間を経て50周年記念誌の良さを改めて認識しつつも、読者にとってより共感できる内容をこの70周年記念誌で目指しました。70年の歴史を誇りに思えるような記念誌を制作することを意識し、取材を行い、紙面構成の検討を行いました」と、読み手の気持ちを意識した姿勢を語ります。
取材現場でみえたジャックスの本質
取材に最も多く立ち会った舛水さんは、「30名ほどの取材に立ち会い、普段は会社について語る機会の少ない方々の生の声を聞くことができました。どの部署の方も真面目に仕事に挑戦し、周りの仲間や先輩、後輩たちに対してもしっかりとリスペクトし、将来のことを真剣に考えている。そういった姿勢は部署や役職を超えて共通していることがわかり、それが一番の発見でした」と語ります。さらに「皆さんの様々な視点や経験をもっと引き出せると、より多角的な記念誌になったかもしれません」と振り返りながらも、「この10年間をけん引してきた3名の社長(板垣氏、山﨑氏、村上氏)全員に登場してもらえたことは本当に良かった。この3名だからこそ、直近10年間の激動の時代を我々は歩めた。それぞれの立場から過去や現在、未来についてしっかりと語ってもらえたことで、経営トップの思いも記念誌に盛り込むことができました」と舛水さん。

次の記念誌づくりへの道しるべ

次の記念誌編纂メンバーへのアドバイスを尋ねると、穴田さんは「どういう記念誌を作りたいかをメンバー内でさらに議論を深めることが大切。次の記念誌は、選ばれたキーパーソンだけではなく、全国で働く従業員全員の写真を何らかの形で掲載できれば一体感がさらに高まると思います」と具体的な提案を語られた。
「どういう記念誌をつくるかを柔軟に考えてほしい。10年後のトレンドや会社の状況によって、その時に必要な記念誌は変わってくるはず。紙からWEBへの展開も検討の余地があります」と石川さんは話します。
小林さんは「次の10年はこれまで以上に変化が大きく、濃い内容になるでしょう。会社のオフィシャルな媒体に登場することに誇りをもってもらえるような企業風土をさらに強化していきたい。この記念誌の価値がさらに高まるのが3年後か5年後かわからないが、その時に会社の歴史や先人たちの想いを伝える大切な役割を果たせるのであれば幸いです」と展望を語られました。
舛水さんからは「毎年の行事や出来事をきちんと記録として残しておくことが大切」というアドバイスと共に、「周年事業全体の中で記念誌の立ち位置(役割)を明確にすること」という示唆に富んだ助言がありました。
プロジェクトを終えた現在の思いを尋ねると、メンバーの皆さんは口をそろえて「制作する中で、これまで先輩方が乗り越えてきた苦労があって今の会社があるということを再認識し、それを周知することの大切さに気づかされました。やっている時は本当に大変だったけれど、今振り返ると本当にやってよかった!」と語っていただきました。このように語る編纂メンバーの想いは読む人の心に確かに届くことでしょう。
「会社が好きな人をもっと増やしたい。そうすれば挑戦しやすく働きやすい、そして業績も上がり、様々な意味で活気のあるもっと良い会社になると思います」という舛水さんの言葉に、70周年記念誌に込められた思いが凝縮されていました。

